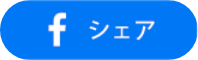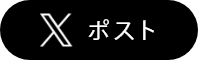2025/03/24
学校給食の歴史を知ろう!食育の「生きた教材」としての役割も
私たちが当たり前のように食べていた給食には、実は深い歴史があり、時代とともに改変が重ねられてきました。そして、現在では食育という観点においても、給食は大きな役割を担っています。今回は、給食の歴史やご当地給食、給食の人気メニューをかつお節でアレンジしたレシピもご紹介しているので、ぜひ試してみてください。

1. 日本の学校給食
日本の学校給食の始まりは、1889(明治22)年に山形県鶴岡町(現・鶴岡市)のお寺の中にある小学校で、生活が困窮している子どもたちに無償で昼食を提供したことが始まりといわれています。当時はおにぎり、焼き魚、漬物という献立でした(注1)。

写真提供元:独立行政法人日本スポーツ振興センター
大正時代に入り給食は徐々に広がっていったものの、戦争によって中断されました。しかし、戦後の食糧難により子どもの栄養状態が悪化し、給食に対する要望が高まったことで給食は再開されました。その後、1954(昭和29)年には「学校給食法」が成立しました(注1)。
学校給食法には「学校給食の目標」が定められており、そのひとつが「適切な栄養の摂取による健康の保持・増進を図ること」です。この目標に基づき、学校給食は栄養バランスを考えて提供されています(注1)。その後、2008(平成20)年には学校給食法が改正され、学校給食を活用して食育を推進することが盛り込まれました(注2)。
現在、学校給食の献立は、管理栄養士資格を持つ栄養教諭などにより「エネルギー」「マグネシウム」「ビタミンC」などの栄養素が1日の推奨量の約1/3を摂取できるよう考えられています(注3)。また「カルシウム」などの不足しがちな栄養素は、学校給食で多めに摂取できるよう設計されています。さらに、食塩相当量は1/3未満が基準で、だしをきかせることで食塩相当量を抑えるなどの工夫がされています(注3)。
2. 給食は食育の「生きた教材」
学校給食は食育の「生きた教材」とされ、食に対する正しい知識や食習慣を身につけ、肥満や朝食欠食といった子どもの食生活における問題を改善できるよう、給食を通じて食育に取り組むことが求められています(注4,5)。

昭和25年度からは、学校の冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」と定め、児童、教職員、保護者、地域住民が、学校給食の役割についての理解を深められるよう、各自治体においてさまざまな取り組みが行われています(注6)。
また、栄養教諭は、献立を立てるだけでなく、食育活動にも取り組んでいます。ある学校では、枝豆やじゃがいもなどの作物を育ててそれを調理したり、豆腐などの加工品を作ったりといった取り組みを行なっています(注7)。また、給食を作る際に出る野菜くずや果物の皮を生ごみ処理機で堆肥にし、食べ残しや分別できていないことの影響を考えるきっかけとしている学校もあります(注8)。
さらに、2013(平成25)年に「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受け、和食文化国民会議では11月24日を「和食の日」と制定しました。和食の日は、日本人の伝統的な食文化を次世代へと保護・継承していくことの大切さを改めて考える日であり、その一環として「だしで味わう和食の日」という和食給食の普及を促進する活動も行われています(注9)。だしで味わう和食の日に参加する学校は、その実施日にかつおだしなどのだしをきかせたメニューや地場産物、郷土料理を盛り込んだ献立を提供しています(注10)。
3. 地域色豊かな全国各地の給食
学校給食では、各地域の食材を使ったメニューや郷土料理、児童からの声を取り入れています。ここではいくつか、ご当地給食メニューをご紹介します。
・イナムドゥチ(沖縄県渡嘉敷村)
沖縄県産の豚三枚肉や、魚のすり身にたっぷりと卵を入れた「カステラかまぼこ」、しいたけ、こんにゃくなどを短冊切りにし、豚骨のだしとかつおだしの合わせだしで煮込み、白みそで味をつけた汁物です。ゴーヤーのあげ煮やドラゴンフルーツゼリーといったメニューを組み合わせ、琉球漆器に盛り付けています(注11)。

出典:農林水産省ウェブサイト
・たこぺったん(東京都大田区)
子どもたちに給食で食べたいメニューのリクエストを募り、その中のひとつだった「たこ焼き」をアレンジしたメニューです。たこ焼き器がない給食室で、中までしっかり加熱して提供するために工夫を凝らし、ぺったんこにして油で揚げた「たこぺったん」が誕生しました(注12)。今でも人気の給食メニューとなっています。
・りっちゃんサラダ
小学1年生の国語の教科書に登場する「サラダでげんき」が元となったサラダで、全国各地の給食で採用されているメニューです。キャベツやきゅうり、ハムなどを千切りにし、しょうゆやみりん、酢、油で作るドレッシングに和えて、かつお節を加えた一品です(注13)。
学校給食には、子どもたちの健康な未来のために栄養バランスから食育活動までさまざまな工夫が詰まっています。ぜひ、ご家庭の献立にも、給食メニューを取り入れてみてはいかがでしょう。
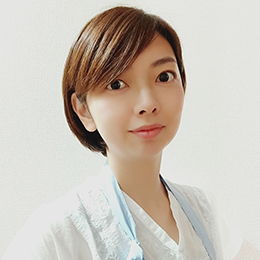
この記事の監修者
荒井名南(あらい めいな)
管理栄養士、フードスペシャリスト、健康食育ジュニアマスター、離乳食アドバイザー
保育園での給食運営や食育指導を経て、「親子のしあわせごはん」をテーマに食育やアレルギー食に関する執筆・監修、中心のレシピ提案などを行う。
参考文献
注1) 農林水産省「ふるさと給食自慢 aff」(農林水産省)
注2) 文部科学省「給食の取組」(文部科学省)
注3) 文部科学省「学校給食の献立はどのように決められているの?」(文部科学省)
注4) 文部科学省「学校における食育の推進・学校給食の充実」(文部科学省)
注5) 文部科学省「学校給食について教えて!」(文部科学省)
注6) 文部科学省「全国学校給食週間について」(文部科学省)
注7) 文部科学省「学校における実践事例」(文部科学省)
注8) 文部科学省「たくましく生きる子をめざして」(文部科学省)
注9) 東海農政局「特別展示『和食の日・郷土料理』」(東海農政局)
注10) 和食文化国民会議「だしで味わう和食の日」(和食文化国民会議)
注11) 農林水産省「沖縄県の学校給食 イナムドゥチ」(農林水産省)
注12) 大田区「食のちからで、子どもたちを笑顔に」(大田区)
注13) 福島県学校給食会「りっちゃんサラダ」(福島県学校給食会)
(参照:2025.03.06)