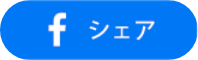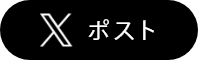だしから作る麺つゆ 追い鰹だしから作る麺つゆ 追い鰹かつお節のうま味や香りをしっかり楽しめる手作りめんつゆです。かつお節のうま味や香りをしっかり楽しめる手作りめんつゆです。
だしから作る麺つゆ 追い鰹だしから作る麺つゆ 追い鰹かつお節のうま味や香りをしっかり楽しめる手作りめんつゆです。かつお節のうま味や香りをしっかり楽しめる手作りめんつゆです。2022/07/29
夏休みに!かつお節を活かした自由研究テーマをご紹介
夏休みの宿題といえば自由研究。
お子さんがテーマ決めに悩んでいる時は、身近な食を活かした自由研究を提案してみてはいかがでしょうか?
かつお節に関する調査や実験など「知らなかった!」「初めて知った、面白い!」と気付きになるようなテーマをご紹介いたします。
●目次1.食に関する自由研究がおすすめの理由2.楽しく自由研究ができるテーマをご紹介テーマ1:かつお節って何?作り方や歴史を調べてみようテーマ2:そばつゆ、そうめんつゆ、うどんつゆを作ってみようテーマ3:食品ロスについて考えようテーマ4:いろいろな場所の郷土料理を調べてみよう3.できたらレポートにまとめましょう!
1.食に関する自由研究がおすすめの理由
食は身近なものであるため興味を持ちやすく、家庭でも簡単に調査や実験ができるためおすすめです。
食卓に並ぶ食材の歴史やルーツ、地域ごとの特徴といった「調べ学習」に繋げることができます。実験が好きなお子さんは、スーパーで売っているめんつゆを自分で再現してみるほか、行ったことがある地域の郷土料理を作ってみると良いでしょう。ほかにも、昨今注目されているSDGsの観点から、食品ロスやエコをテーマにして調べ学習や実験を行うこともできます。
食を大きな題材にさまざまな切り口で自由研究のテーマを見つけてみましょう。
2.楽しく自由研究ができるテーマをご紹介
冷奴やお好み焼きのイメージが強いかつお節。実は、かつお節はトッピングだけではなくだしとしても使用されていて、味噌汁やうどん、煮物など和食を中心にさまざまな料理において重要な役割を担っています。
さらに、食べ物をおいしくしてくれるうま味成分が多く入っていたり、たんぱく質が豊富に含まれていたりと、かつお節が持つ特徴や魅力はさまざまです。
また、かつお節の歴史は古く、日本人に愛され続けている食材のひとつでもあります。
テーマ1:かつお節って何?作り方や歴史を調べてみよう
かつお節の原料が魚だと知っていますか?お子さんに聞いてみると、意外な答えが出てきて驚くかもしれません。最近では、ご家庭でかつお節を削ることは少なくなったため、削る前の状態は見たことがない人も多いですよね。そこで、かつお節とはどんな食材か、調べ学習をしてみましょう。
かつお節が何からできているのか、どうやってできているのかといった作り方を調べるほか、世界中の食べ物の中でも「硬い食べ物」として知られているかつお節の特長や削り方などをまとめてみると、かつお節への理解をはじめ「日本の食文化」への興味、「和食について」の理解が深まります。
ほかにも、生産地など地域ごとの特徴について調べてみるのも良いでしょう。かつお節にはどのような栄養素が含まれていて、体内でどのように働くのかを調べるのもおすすめです。
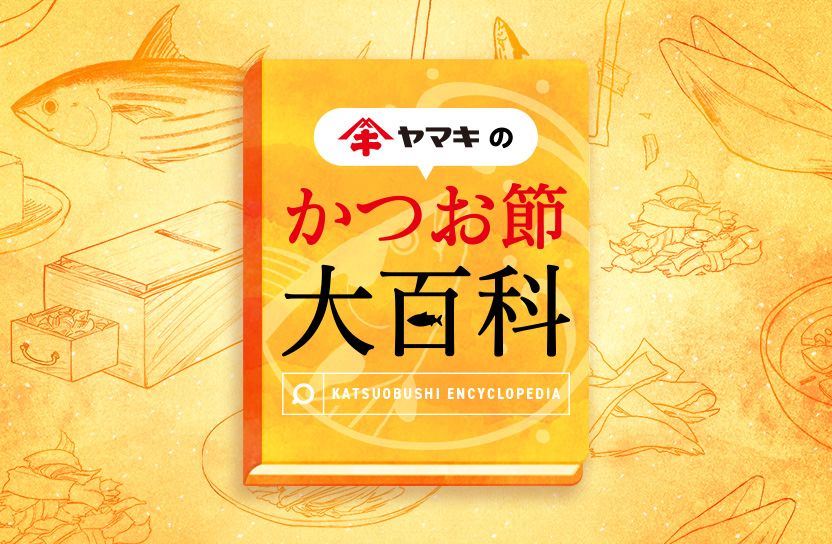 かつお節大百科鰹節屋のヤマキがお届けする
かつお節大百科鰹節屋のヤマキがお届けする
かつお節の百科事典!
様々なかつお節に関する知識を
ご紹介します!詳しくはこちら詳しくはこちら
テーマ2:そばつゆ、そうめんつゆ、うどんつゆを作ってみよう
普段そばやそうめん、うどんなどを食べる時に使うめんつゆでも、かつお節が活躍しています。かつお節からだしを取って醤油などの調味料で味付けし、お家で再現してみたらどんな味になるのか試してみましょう。
そば・そうめん・うどんのつゆの味の違いについてまとめてみるほか、だしの種類を変えてみたり、だしを入れずに作ってみたりするなど条件を変えてみると、香りや風味など、めんつゆにおけるだしの役割について気付きを得られるでしょう。
ベースとなるめんつゆの作り方を参考にしながら、だしや調味料の配合を変えて、実験してみてはいかがでしょうか。
だしを取った後のだしがらはふりかけなどに活用できるのでチャレンジしてみるものいいですね。
テーマ3:食品ロスについて考えよう
食品ロスとは何か、ご家庭で考えてみましょう。
日本人は毎日1人あたりお茶碗1杯分に近い量のご飯を捨てていると言われており、食品ロスの量は年間約41kgにもなると言われています。嫌いなものを残してしまったり、食べきれなくて捨ててしまっていたりしませんか?(注1)
ご家庭から出る食品ロスの量や種類を調査してみるほか、野菜の切り方を工夫して食品ロスを減らす方法を考えて試してみましょう。
食事を残さないための方法について話し合ってみるのもいいですね。
つい残してしまう苦手な野菜はかつお節でおいしく食べることができるかもしれません。この夏に、ピーマンやゴーヤなど苦手な野菜を克服しながら食品ロスについて考えてみるのはいかがでしょうか。
 野菜嫌いにかつお節!
野菜嫌いにかつお節!
かけるだけで食べやすく!ピーマンやゴーヤの苦味を克服⁈
野菜の苦味を和らげて、
もっとおいしく食べられる
かつお節活用術をご紹介します。詳しくはこちら詳しくはこちら
ほかにも、かつおだしを取った後のだしがらなど、普段は捨ててしまいがちなものを活用した料理に取り組むと、食材を無駄にしない意識が芽生えます。
テーマ4:いろいろな場所の郷土料理を調べてみよう
かつお節は各地域に根付いた料理でも活躍しています。
かつお節を使った郷土料理にはどんなものがあるか調べてみるほか、実際に作って食べてみましょう。住んでいる地域以外の特徴や新しい味を発見することができます。郷土料理にかつお節が使用されている理由や、その料理が生まれた背景なども一緒に調べてみると、その地域の知らなかったことや新しい発見があるかもしれません。
 おいしさ発見!
おいしさ発見!
かつお節マップ鰹節屋のヤマキがおすすめする、
かつお節が活躍する料理を
集めてみました!
全国で
活躍するかつお節を見てみよう!詳しくはこちら詳しくはこちら
3.できたらレポートにまとめましょう!
自由研究ができたら、頑張った研究をしっかり読んでもらうためにも、分かりやすくレポートにまとめましょう。
レポートは基本的に、調べようと思ったきっかけ・調べた結果・まとめの順に書きます。
⚫︎調べ学習の場合
はじめに、この自由研究をしたいと思った理由を書いてから、調べた方法や結果を書いていきます。まとめの部分に自分の考えや新しい疑問点、感想などを書きましょう。
最後に、実験で参考にした本やWebサイトの名前を記しましょう(注2)。
写真やイラスト、絵を入れるほか、色鉛筆などで見てほしいところを強調したり、随時見出しをつけると読みやすいレポートを作ることができます。
⚫︎実験や料理の場合
はじめに、実験を思いついたきっかけと仮説を書きます。
次に、材料と実験方法、実験して分かったことを書いていきます。実験方法は他の人が同じ実験をしても同じ結果になるように書くことがポイントです。
まとめには新しい発見や感想、自分の考えを述べます。最後に、実験で参考にした本やWebサイトの名前を記しましょう(注2)。
写真やイラストを使って実験を説明すると、分かりやすいレポートになります。
自由研究を発表するときは、調べてみて良かったことをまとめて話すと、聞く人が「楽しそう、やってみたいな」と思えます。自分のやった自由研究を宣伝するつもりで話してみましょう(注3)。
お子さんがレポートの書き方に悩んだときは、ぜひ参考にしてみてください。


この記事の監修者
渡部 早紗
管理栄養士
管理栄養士を取得後、病院管理栄養士として献立作成や栄養指導に携わる。その後、学校給食関連の企業にて調理・衛生指導を経験。現在はフリーランスとして食や栄養に関するコラム執筆・監修・健康商材の広告制作を中心に活動し、言葉による健康発信を行う。
脚注:
注1) 「食品ロスとは」(農林水産省)(参照:2022.05.20)
注2) 『お父さんが教える自由研究の書きかた』 (㈱自由国民社、2009年)
注3) 『小学校の先生たちが教える おもしろ自由研究』(㈱あゆみ出版、1996年)