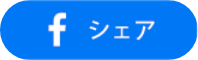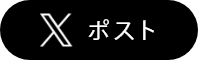2025/04/24
旬のたけのこを楽しもう!選び方や保存方法、おいしい食べ方を解説!
春は、生のたけのこを楽しめる貴重な季節です。たけのこの魅力を知ったうえで味わえば、よりおいしく感じることができます。たけのこの選び方やアク抜きの方法など調理方法を知り、たけのこ本来のおいしさを堪能しましょう。
1. たけのこの基本 漢字「筍」の由来から品種まで
たけのこの漢字は、竹冠に旬で「筍」と書きます。この漢字は、たけのこの成長スピードが驚くほど早く、一旬(いちじゅん、10日間)で竹になることが由来だといわれています(注1)。

一般的に、店頭で購入できるたけのこの品種は「モウソウチク(孟宗竹)」といいます。鹿児島県南部では、早掘りたけのことして12月頃から出荷されますが、通常は、3月頃から九州で収穫され、徐々に産地が北へ移行していき5月頃まで収穫されます。
そのほか、細身で皮に黒いまだら模様があるのが特徴の「マダケ(真竹)」は5月から6月頃が旬です。赤茶色の薄い皮に包まれた少し細身の「ハチク(淡竹)」は5月に旬を迎えます(注2)。3月から5月にかけて、さまざまなたけのこを目にする機会が増えると思いますが、旬を見逃さないように時期を把握しておくとよいでしょう。
2. ここがポイント!たけのこの選び方
せっかくたけのこをいただくなら、おいしく食べたいですよね。ここでは、おいしいたけのこの選び方のポイントをお伝えします。
・皮
皮は、なるべく薄茶色のものを選びましょう。皮の色が黒に近かったり、緑色がかっていたりするものは日光に当たっているので、アクも強くなります(注2)。
・穂先
穂先はなるべく黄色っぽいものを選び、緑色のものは避けましょう。黄色の穂先は土から出ていない証拠です。たけのこは、土から頭を出すと光合成を行うため、穂先が緑になり、えぐ味が増します(注2)。えぐ味の量は、日光に当たったかどうかに左右されます(注3)。
・根元
根元近くのポツポツの色が薄ければ、収穫後時間が経過していない新鮮なたけのこです。この色が薄ければ薄いほど、切り取ってから時間が経っておらず、えぐ味が少なくなっています(注3)。
3. たけのこのアク抜きとおいしく保存する方法
新鮮でおいしいたけのこも生のまま置いておくと、時間の経過とともにえぐ味が増してしまいます。そのため、たけのこを購入したらすぐにぬかと一緒に茹で、アク抜きをするのがポイントです(注3)。ここでは、下茹でによるアク抜きや保存方法を解説します。

・アク抜き
茹でるときは、皮つきのまま先端を大きく斜めに切り、皮の部分に縦に切れ込みを入れましょう。その後、大きな鍋に水を入れ、たけのことひと掴みのぬかを一緒に入れて火にかけます。沸騰したら弱火にして、根元に串が通ったら火を止めてください。40~50分が目安です(注4)。
・保存方法
アク抜きをしたたけのこは、皮を剝いて水に浸して、密閉容器に入れて冷蔵庫で冷やしましょう。通常1週間保存できます(注4)。冷凍する場合は、使いやすいように食べやすい厚さ(5mm程度)に切って保存しましょう。ただし、そのまま冷凍するとスカスカになってしまうので、砂糖をまぶして冷凍するのがおすすめです。こうすることで、たけのこの味を損ねにくいといわれています(注5)。
・アク抜き不要で便利な市販のたけのこの水煮
生のたけのこのアク抜きは少し手間がかかります。この工程を省きたい場合には、たけのこの水煮が便利です。アク抜き不要な市販の水煮ですが、水煮特有の臭いもありますので、一度湯通ししてから醤油などにつけて食べることをおすすめします。ちなみに、水煮のたけのこについている白い粒は、たけのこに含まれる「チロシン」というアミノ酸です。食べても問題はありません(注6)。
4. たけのこをよりおいしく食べるには
たけのこにはうま味成分である「グルタミン酸」が含まれています(注4,7)。そのため、同じうま味成分である「グアニル酸」が含まれている干し椎茸や、「イノシン酸」が含まれているかつお節などと組み合わせると相乗効果でよりおいしく食べることができます(注7,8)。
たけのこ料理には、かつおだしで炊いたたけのこご飯や、かつお節を使った土佐煮、たけのこの和え物などたくさんあります。ぜひかつお節と一緒に食べてみてください。

たけのこは、シンプルでありながら食感や香りから季節の変わり目を感じさせてくれる食材です。ぜひ、春には、たけのこを使った料理に挑戦してみましょう。

この記事の監修者
尾澤 真紀(おざわ まき)
管理栄養士・公認スポーツ栄養士・栄養教諭
フィットネスクラブやJリーグクラブの管理栄養士を経験。現在は、甲子園常連校のスポーツ栄養サポートや、専門学校・高校の非常勤講師などを担当している。
参考文献
注1) 農林水産省「たけのこ aff(2020年3月)」(農林水産省)
注2) 農林水産省「これからが旬!たけのこで『春』を感じよう aff(2021年3月)」(農林水産省)
注3) 全国農業協同組合連合会 愛媛県本部「たけのこ えひめの食」(全国農業協同組合連合会 愛媛県本部)
注4) JAグループ「春の旬食材タケノコ(筍) とれたて大百科」(JAグループ)
注5) 『農家が教えるタケノコづくし』(一般社団法人農山漁村文化協会、2022年9月25日)
注6) コープ北陸事業連合「組合員Q&A」(コープ北陸事業連合)
注7) 農林水産省「たけのこご飯 宮城県 うちの郷土料理」(農林水産省)
注8) 国立がん研究センター東病院「調理のポイント うま味の活用」(国立がん研究センター東病院)
(参照:2025.03.14)