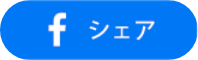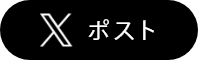2025/04/28
ふりかけの歴史を学ぼう!家庭で楽しめる手作りふりかけも紹介
ご飯のお供の代表格である「ふりかけ」。その原料には、かつお節などの日本の伝統的な乾物がよく使われるのも特徴です。ふりかけの歴史や人気の理由、ご家庭で楽しめる手作りふりかけなどをご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 時代とともに変化するふりかけ
ご飯にサッとかけて食べられる「ふりかけ」は、味のバリエーションも豊富で、食事に取り入れやすい調味乾製品です(注1)。
ふりかけには、かつお節などの乾物を使用することがあります。乾物の歴史は古く、日本最古の料理書のひとつ「厨事類記(ちゅうじるいき)」には、魚や肉を細長く切って干した「すわやり」や「そわやり」と呼ばれる食べ物があったことが記されています(注2)。

大正時代の初めになると、熊本の薬剤師「吉丸末吉」が、カルシウムを補うために小魚を乾燥させて粉にして調味し、ごまやケシの実、青のりなどを加えたものをご飯にかけることを考案しました。これが、現代のふりかけのはじまりとも考えられます(注3)。魚嫌いの人でも、おいしく食べられるよう、ほかの材料を混ぜ、魚臭くならないように工夫して考案されたそうです(注3)。
2. ふりかけの消費量は増えている
総務省の家計調査によると、二人以上の世帯におけるふりかけの消費量は近年増加しており、2024年度(令和6年度)におけるふりかけの支出金額は、前年比の110.6%増となっています(注4)。この背景としては、物価高や感染症の拡大が影響しているという見方もあるようです。

ふりかけを使う家庭が多くなったことに加え、感染症の拡大によりおうち時間が増えたことで、食卓におけるふりかけご飯が習慣化した家庭も少なくありません。また、レシピ情報がスマートフォンなどで手軽に得られることから、料理をする層が増え、お弁当を作る人が多くなったり、家庭でおにぎりの作り置きが浸透したりするなど、市場拡大の一因となっています(注5)。
さらに、ふりかけには、かつお節やのり、小魚などの天然素材を使った伝統的な乾物が含まれることが多く、ふりかけが高く評価されている理由のひとつです(注5)。
3. かつお節はふりかけにぴったり
かつお節は、そのままご飯にかけるだけで、おかかごはんとしておいしくいただけますし、ほかの材料と合わせれば、簡単にオリジナルのふりかけを作ることができます。たとえば、刻んだ大根葉やザーサイなどとかつお節を合わせてサッと炒めれば、ご飯をもっとおいしくいただけるでしょう。

また、かつお節でだしをとった後に残る「だしがら」を活用するのもおすすめです。だしがらにはかつお節のうま味が残っており、めんつゆを絡めて煎るだけで、おいしいふりかけができあがります(注6)。ごまや海苔など、お好みの材料を加えて、自由にアレンジするのもおすすめです。ぜひ、かつお節やだしがらを活用して、ご家庭でおいしいふりかけを作ってみてください。
古い歴史を持つふりかけは、現代も食卓を支えるアイテム。かつお節を使ってご家庭でも作れるので、この機会にぜひチャレンジしてみてください。
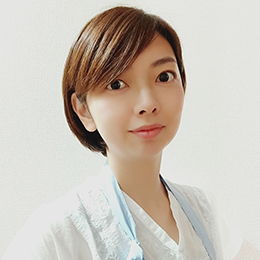
この記事の監修者
荒井名南(あらい めいな)
管理栄養士、フードスペシャリスト、健康食育ジュニアマスター、離乳食アドバイザー
保育園での給食運営や食育指導を経て、「親子のしあわせごはん」をテーマに食育やアレルギー食に関する執筆・監修、レシピ開発などを行う。
参考文献
注1) 農林水産省「調味加工品」(農林水産省)
注2) 千葉市「千葉氏フォーラム議事録」(千葉市)
注3) 日本食糧新聞「ふりかけ・お茶漬け特集 ふりかけの歴史 大正時代に熊本で」(日本食糧新聞)
注4) 総務省「家計調査 1. 品目分類:支出金額・名目増減率・実質増減率」(総務省)
注5) 日本食糧新聞「ふりかけ・お茶漬け特集:ふりかけ=過去最高更新へ 節約志向応える徳用感」(日本食糧新聞)
注6) ヤマキ「だしがらの活用方法」(ヤマキ株式会社)
(参照:2025.04.23)